先日15日に竣工した住宅の母屋と離れ。
母屋に作った天窓は光の波長が短い朝の仕様にした。
海の底から見上げた色調になった。
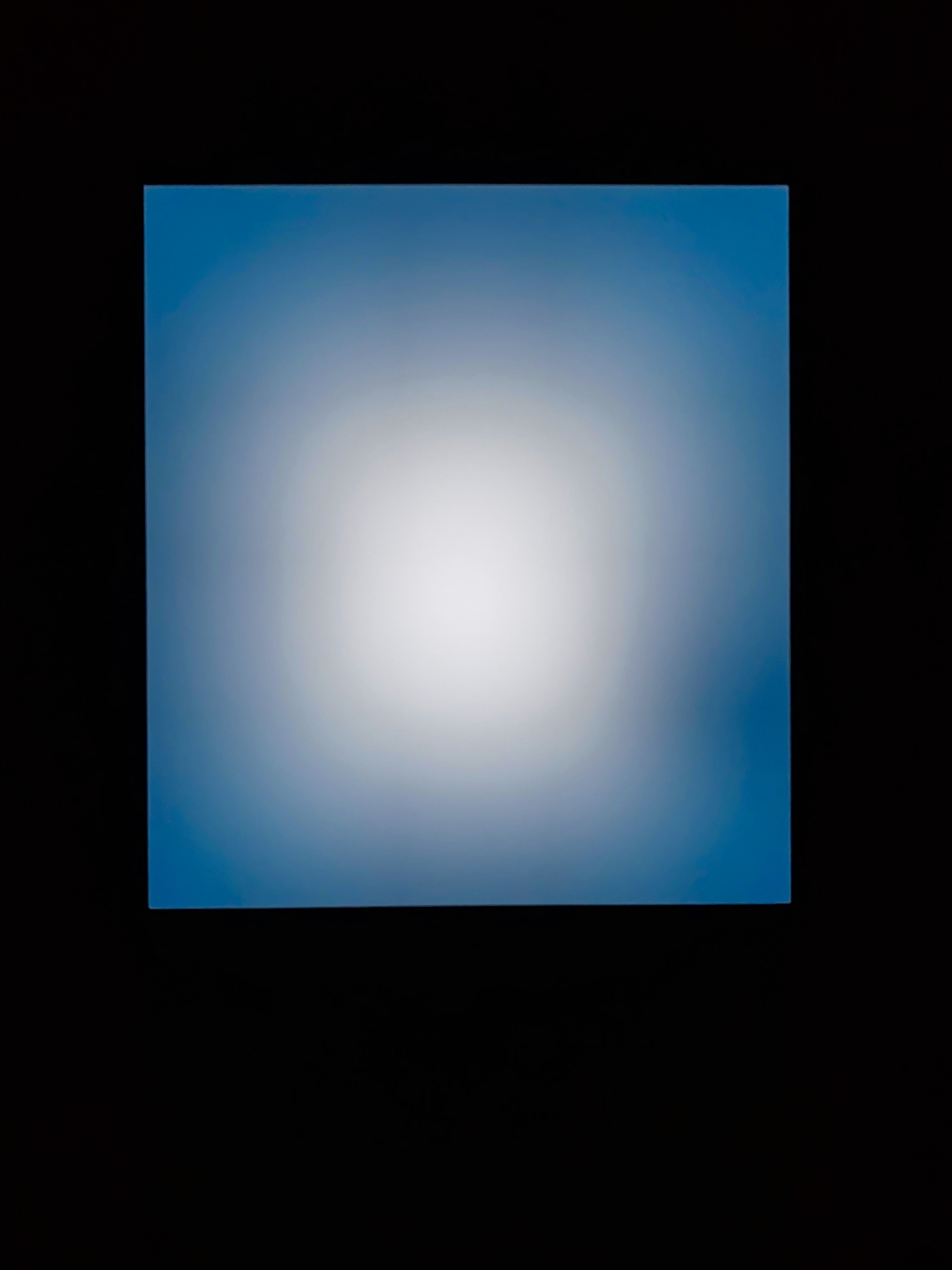
離れの入り口は両開きに。その内側にステンレス格子で挟んだ防虫網を引き戸にした。

建築の世界に入るきっかけをくれた逸見さん。
京都で数寄屋の修行を終え帰岡し、仕事を続けていた。
大きな体で滑らかにゆっくり動く。
凪の如く決して誰にも怒ったりなどしない。
いつもうす汚れていたが、品があり諦観を漂わせていた。
規矩尺術を巧みに使いこなし、曲尺をくるくると回す。
黙々と滑らかに刻みものを組み上げる。
たまに出来たものが気に入らないと、工期や予算などお構いなしに黙々と壊す。
何も分かっていない私に、
「たとえば拳大の石があるとするじゃろう。ほんとに拳くらいの大きさなんか、
土の中の大きな石の先端なんか感じてわかる様にならんといけん」
この人ほんとに分かるんかなあと思いながら「はい」と返事をした。
「仕事」事に仕える。
自分の感覚に従って「美」を追求する真摯な姿勢を思い出し
今でもやはり憧れである。

竣工と同時によく作る木のオリジナルポスト。
材料はたも、内寸横410ミリ縦300ミリ。
普通封筒は小口の穴から投函。

大型封筒は上の蓋を上げて投函。

取り出す時は全面がOPENになる。通常はネオジム磁石で蓋は半固定するが
防犯が気になればダイアルキーも付けられ、外壁の色に合わせて木の目が消えないように塗装する。


3年前に竣工したcalmeの小庭の刷新。
上部は開放して夜露が入るようにしてある。植物が育つ重要な役割があるが
近年の短時間での雨量の多さは困りものだ。

水苔が環境に合わず傷んでしまったので全て除去をした。
庭の高さも少しあげて作り直す。

痩せた黒土を全体に使い、木々の間に雑草も混ぜて植える
飾らない素朴な自然の切り取りです。
雨が降ると高低差によって溜まりながら流れていくようにした。





